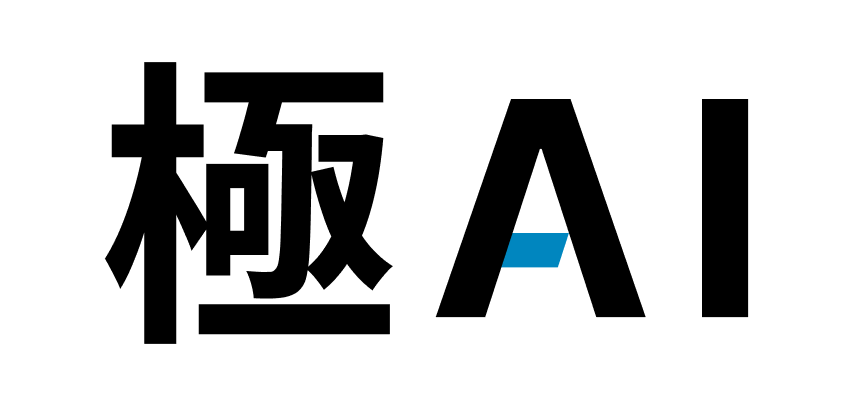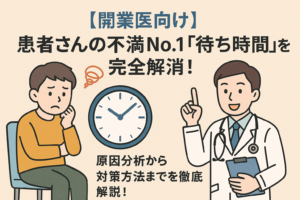【令和6年度改定対応】診療情報提供料(I)・紹介状の算定要件と加算をどこよりも詳しく解説!
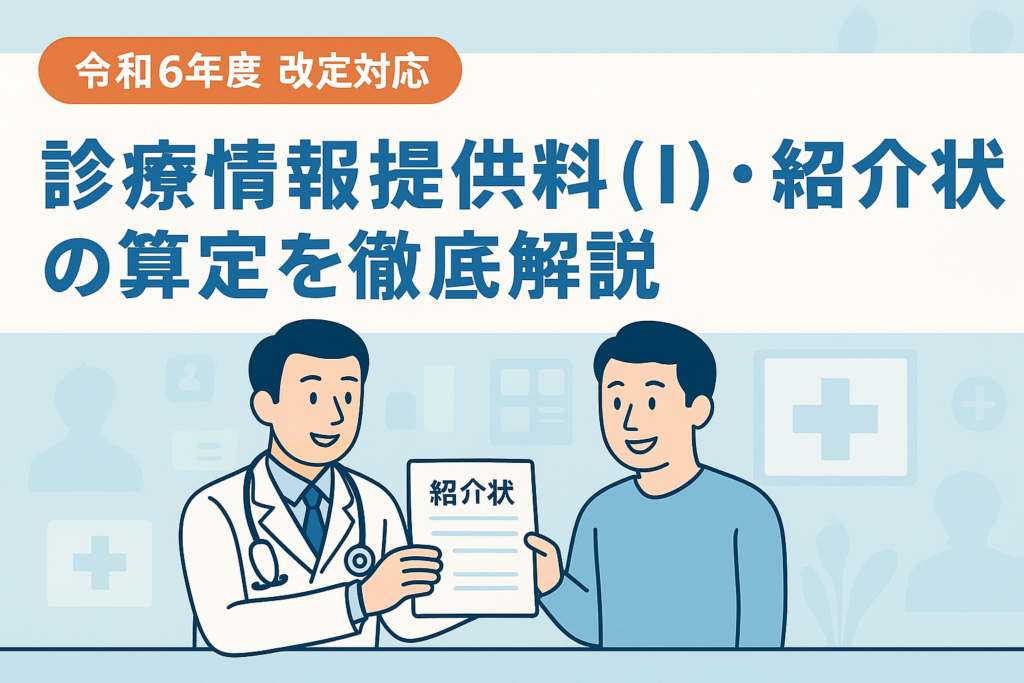
クリニックを運営されている先生方にとって、他の医療機関や施設との連携は日常的な業務かと思います。その際に作成する「紹介状」、正式には「診療情報提供書」ですが、これには**診療情報提供料(I)**という形で診療報酬が設定されています。
この点数は、患者さんの診療情報を他の機関と適切に共有し、切れ目のない医療を提供するための大切な評価です。今回は、この診療情報提供料(I)について、特に令和6年度診療報酬改定(令和6年6月1日施行)の内容を踏まえ、算定の基本ルールと加算について分かりやすく解説します。
診療情報提供料(I)とは? – 基本をおさらい
診療情報提供料(I)は、先生が患者さんの診療に基づき、「他の医療機関での専門的な治療や検査が必要だ」「介護サービスのために情報提供が必要だ」と判断した場合に、患者さんの同意を得て、診療情報提供書(紹介状)を作成・提供した際に算定できる点数です。
単なる文書作成の手間賃ではなく、医療機関同士や、医療と介護・福祉などがスムーズに連携するための重要な仕組みと位置づけられています。
基本点数と算定のルール(令和6年度改定)
まずは基本となる点数と、算定するための共通ルールを確認しましょう。
- 基本点数: 250点
- 算定頻度: 紹介先の医療機関や施設ごとに、患者さん1人につき月1回に限ります。
- 患者さんの同意: 情報を提供する前に、必ず患者さん(場合によってはご家族など)から同意を得る必要があります。
- 文書の提供: 診療情報提供書を作成し、紹介先に渡す(郵送なども含む)ことが必要です。
- 診療録への記録: 提供した文書の写しを診療録に添付するか、内容を記録して保管しなければなりません。これは非常に重要です!
- 紹介の必要性: 先生が診療の結果、他の機関での診療などが必要だと判断していることが大前提です。
どこに紹介すると算定できる? 紹介先別のポイント
診療情報提供料(I)は、紹介先によって算定できるケースが具体的に定められています。主なものを確認しましょう。
- 他の保険医療機関へ紹介する場合:
- より専門的な診断や治療、精密検査、あるいは自院にない設備での検査・画像診断などを依頼する場合に算定できます。
- 自院に設備がないため、他の医療機関(特別の関係にある施設を除く)に検査や画像診断を依頼する場合も対象です。この時、依頼先の医療機関が読影結果などを文書で返してくれた場合、依頼先の医療機関も診療情報提供料(I)を算定できます(単なる場所貸しのような場合は算定不可)。
- 市町村や保健・福祉サービス関連機関へ情報提供する場合:
- 患者さんがお住まいの市町村、ケアマネジャー(指定居宅介護支援事業者)、相談支援専門員(指定特定相談支援事業者)などに、保健福祉サービスに必要な情報を提供する場合です。
- 原則として、在宅療養中で、今後も在宅での生活が見込まれる患者さんが主な対象です。
- 保険薬局へ情報提供する場合:
- 在宅での療養中で通院が難しい患者さんについて、薬局による在宅訪問(在宅患者訪問薬剤管理指導)が必要と判断し、患者さんの同意を得て、服用中の薬や服薬状況などの情報を提供する場合です。
- 精神障害者施設や介護保険施設などへ情報提供する場合:
- 精神障害者支援のグループホーム(福祉ホーム等)や、介護老人保健施設(老健)、介護医療院に入所(または通所)している患者さんについて、社会復帰などを目的として施設に情報提供する場合です。
- 【令和6年度改定】 令和7年10月1日から、情報提供先に**「就労選択支援事業所」**が追加されます。精神障害のある方の就労支援との連携が評価されるようになります。
- 介護老人保健施設(老健)・介護医療院へ直接紹介する場合:
- 患者さんの入所を目的として、老健や介護医療院に直接紹介する場合です。
- 認知症専門医療機関へ紹介する場合:
- 認知症が疑われる患者さんについて、鑑別診断などのために専門医療機関(認知症疾患医療センターなど)に紹介する場合です。
- 保育所・学校などへ情報提供する場合:
- 小児慢性特定疾病のお子さんや、医療的ケアが必要な障害児、アナフィラキシーの既往がある食物アレルギーのお子さんなどについて、患者さん・ご家族の同意を得て、通っている保育所や学校の学校医などに、園・学校生活で必要な配慮などの情報を提供する場合です。
うっかりミスに注意!算定上の留意点
算定要件が細かいため、意図せず誤った請求をしてしまうケースや、算定漏れが起こりやすい点数でもあります。個別指導などで指摘されやすい点には特に注意しましょう。
- よくある算定NG例:
- 主治医が自分自身(同じ医療機関内の別部署など)に情報提供した。
- 紹介元への返書(患者さんが紹介元に戻らない場合)で算定した。
- 紹介状に具体的な紹介先機関名が書かれていなかった。
- 診療録への写し添付は必須!: 提供した紹介状のコピーを必ず診療録に添付・保管してください。これが無いと、点数が認められません。
- 査定・返還リスク: 要件を満たさない請求は、審査支払機関での査定(減点)だけでなく、個別指導で指摘され、過去に遡って返還を求められる可能性もあります。
正確な算定のためには、同意取得、文書作成、診療録への記録という一連の流れをしっかり行うことが大切です。医師事務作業補助者を活用されているクリニックも多いかと思いますが、最近は、極 医療文書のようなAIシステムで紹介状作成を行うシステムも出てますので、これらの活用も有効でしょう。
点数アップのチャンス!主な加算一覧(令和6年度改定)
診療情報提供料(I)には、基本点数(250点)に加えて、特定の連携をさらに評価するための「加算」が多数用意されています。より質の高い情報連携や、国が推進したい連携体制への貢献が点数として評価される仕組みです。
以下に、主な加算の点数と算定のポイント(令和6年度改定基準)をまとめました。
- 退院時情報提供加算 (200点):
- 患者さんの退院月かその翌月に、転院先や入所先の施設(他の病院、精神科施設、老健、介護医療院)に、退院後の治療計画や検査結果、画像情報などを添えて情報提供した場合。
- ※後述の「検査・画像情報提供加算(イ)」を算定する場合は算定できません。
- ハイリスク妊婦紹介加算 (200点):
- 「ハイリスク妊産婦共同管理料(I)」の届出医療機関が、ハイリスク状態の妊産婦さんを連携先の医療機関に紹介する際、必要な情報を添付した場合(妊娠中1回限り)。
- 認知症専門医療機関紹介加算 (100点):
- 認知症疑いの患者さんを、鑑別診断などのために専門医療機関(認知症疾患医療センター等)に紹介した場合。
- 認知症専門医療機関連携加算 (50点):
- すでに認知症と診断されている外来患者さんで、症状が悪化した場合などに、かかりつけ医として専門医療機関に再度情報提供した場合。
- 精神科医連携加算 (200点):
- 精神科以外のクリニックが、うつ病などを疑う患者さんを、精神科医療機関に予約を取った上で紹介した場合。
- 肝炎インターフェロン治療連携加算 (50点):
- 長期のインターフェロン治療が必要な肝炎患者さんを、治療計画に基づき専門医療機関へ紹介した場合。
- 歯科医療機関連携加算1 (100点):
- 医科の先生が、患者さんの口腔機能管理が必要と判断し、歯科医療機関へ紹介した場合(がん治療中など)。
- 歯科医療機関連携加算2 (100点):
- 周術期などで口腔機能管理が必要な患者さんを、歯科医療機関に予約を取った上で紹介した場合。
- 地域連携診療計画加算 (50点):
- 地域連携パスに基づいて退院した患者さんについて、退院後の診療を担当する医療機関が、退院元の病院に患者さんの状況などを情報提供した場合。
- 療養情報提供加算 (50点):
- 患者さんが入院・入所する病院や施設へ情報提供する際に、普段その患者さんを担当している訪問看護ステーションから得た療養情報を添付した場合。
- 検査・画像情報提供加算:
- イ:退院患者の場合 (200点)
- 退院月または翌月に提供。退院時情報提供加算とは併算定不可。
- ロ:入院患者以外の場合 (30点)
- 算定要件: 紹介時に、主要な診療記録(検査結果、画像情報、所見、投薬内容、退院時要約(イの場合)等)を、電子的な方法(①医療情報ネットワーク経由で常時閲覧可能にする、②電子的な紹介状に添付して送受信する、のいずれか)で提供した場合に算定できます。施設基準の届出が必要です。
- この加算は、単なる紹介状のやり取りだけでなく、検査データや画像といった具体的な臨床情報を電子的に共有することを評価するものです。特に退院時(イ)の点数が高いのは、スムーズな情報連携の重要性を示しています。医療DXの流れとも合致する加算と言えます。
- イ:退院患者の場合 (200点)
表:診療情報提供料(I)の主要な加算(令和6年度)
| 加算名 (略称可) | 点数 | 主な算定要件(概要) |
| 退院時情報提供加算 | 200点 | 退院月または翌月、転院/入所先に治療計画・検査結果等を添付して紹介。検査・画像情報提供加算(イ)との併算定不可。 |
| ハイリスク妊婦紹介加算 | 200点 | 特定のハイリスク妊産婦を共同管理下の連携医療機関に情報添付して紹介(妊娠中1回)。 |
| 認知症専門医療機関紹介加算 | 100点 | 認知症疑い患者を専門医療機関(認知症疾患医療センター等)に鑑別診断等のため紹介。 |
| 認知症専門医療機関連携加算 | 50点 | 診断済みの認知症外来患者の症状増悪時に、専門医療機関へ再度紹介。 |
| 精神科医連携加算 | 200点 | 非精神科が精神疾患疑い患者を、精神科に予約を取った上で紹介。 |
| 肝炎インターフェロン治療連携加算 | 50点 | 長期インターフェロン治療が必要な肝炎患者を、治療計画に基づき専門機関へ紹介。 |
| 歯科医療機関連携加算1 | 100点 | 医科が口腔機能管理が必要な患者(がん治療中等)を歯科へ紹介。 |
| 歯科医療機関連携加算2 | 100点 | 周術期等の口腔機能管理が必要な患者を、歯科に予約を取った上で紹介。 |
| 地域連携診療計画加算 | 50点 | 地域連携パスで退院した患者について、外来診療医が退院元病院へ情報提供。 |
| 療養情報提供加算 | 50点 | 入院/入所先への情報提供時に、訪問看護ステーションからの療養情報を添付。 |
| 検査・画像情報提供加算 (イ) | 200点 | 退院患者について、主要な診療記録(検査・画像・退院時要約等)を電子的に提供(ネットワーク経由or添付)。施設基準あり。退院時情報提供加算との併算定不可。 |
| 検査・画像情報提供加算 (ロ) | 30点 | 入院患者以外について、主要な診療記録(検査・画像等)を電子的に提供(ネットワーク経由or添付)。施設基準あり。 |
終わりに
今回は、診療情報提供料(I)の基本と加算について解説しました。算定要件は細かい部分もありますが、患者さん中心の連携を推進するための大切な評価です。日々の診療の中で、適切な情報提供と算定が行えるよう、この記事がお役に立てれば幸いです。
また、最近では、「極 医療文書」のような、AIを活用して、紹介状を作成するシステムも登場しています。このようなAIツールを活用して、ぜひスムーズな紹介状作成を進めていきましょう。