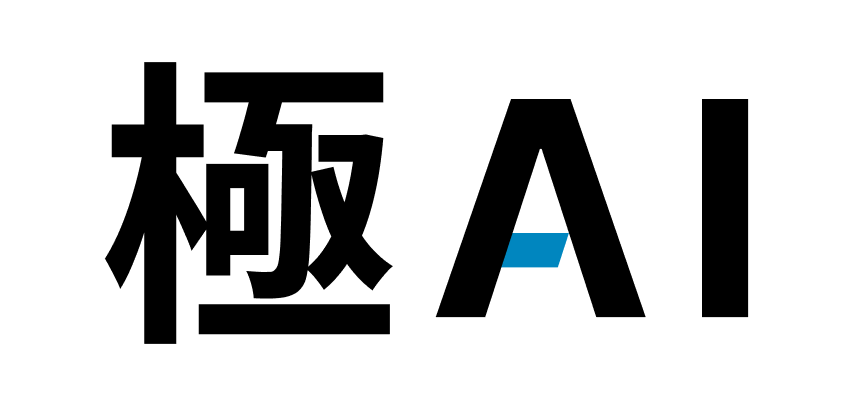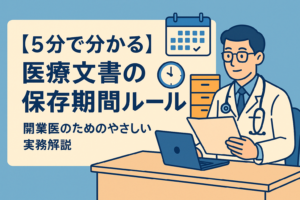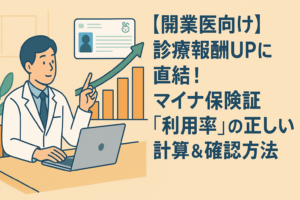【2025年最新版】医療DX推進体制整備加算:届出・算定要件を“確実”に押さえるポイント解説
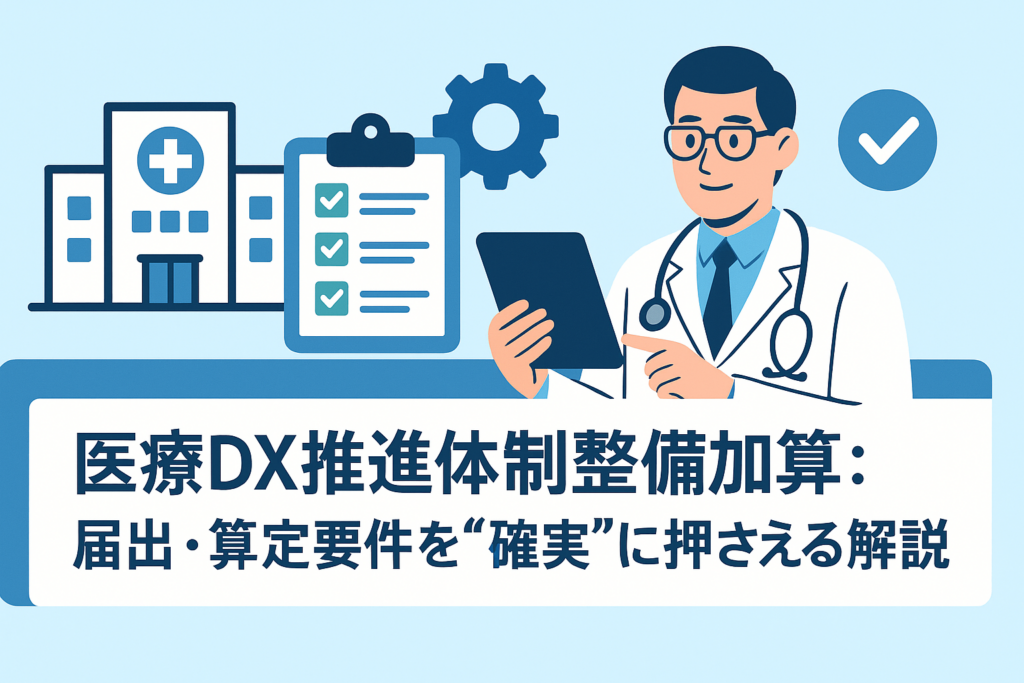
令和6年度診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」。先生方のクリニックでは、もう届出はお済みでしょうか?「よくわからないまま時間が過ぎてしまった」「何から手をつければいいの?」と感じている先生もいらっしゃるかもしれません。
この加算は、国が進める医療DXに対応する体制を評価するもので、今後のクリニック運営において重要性が増しています。
この記事では、多忙な開業医の先生方のために、「医療DX推進体制整備加算」のポイントを絞り、届出方法や算定要件、注意点などを分かりやすく、実践的に解説します。
そもそも「医療DX推進体制整備加算」って何?(ポイントまとめ)
- 目的: オンライン資格確認システムなどを活用し、質の高い医療を提供するための体制(医療DXの基盤)が整備されているかを評価します。
- 背景: 国の「医療DX令和ビジョン2030」に基づき、マイナ保険証の利用促進や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの普及を目指しています。
- 点数: 初診時に月1回算定できます。点数は、マイナ保険証の利用率と電子処方箋の発行体制の整備状況に応じて、令和7年4月から以下の6段階になっています。
| 加算区分 | 医科点数 | 主な要件(マイナ保険証利用率 / 電子処方箋) |
|---|---|---|
| 加算1 | 12点 | 利用率45%以上 / 導入済 |
| 加算2 | 11点 | 利用率30%以上 / 導入済 |
| 加算3 | 10点 | 利用率15%以上* / 導入済 |
| 加算4 | 10点 | 利用率45%以上 / 未導入 |
| 加算5 | 9点 | 利用率30%以上 / 未導入 |
| 加算6 | 8点 | 利用率15%以上* / 未導入 |
* 小児科外来診療料を算定し、6歳未満患者割合が3割以上の医療機関は、令和7年9月30日まで12%以上。
参考)厚生労働省 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し
加算算定のための「必須条件」チェックリスト
この加算を算定するには、以下の基準をすべて満たす必要があります。
- ☐ オンライン請求を実施している
- ☐ オンライン資格確認を行う体制がある
- ☐ 取得した診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制がある
- 単にシステムがあるだけでなく、実際の診療現場で情報を見られることが重要です。
- ☐ 電子処方箋を発行する体制がある
- 【重要】令和7年4月以降、この体制の有無で加算点数が大きく変わります(加算1~3 vs 加算4~6)。 経過措置は令和7年3月31日で終了しました。
- ☐ 電子カルテ情報共有サービスを活用する体制がある
- 【注意】令和7年9月30日までは経過措置がありますが、それ以降は対応必須となるため、早めの準備・確認(ベンダーへの問合せ等)が推奨されます。
- ☐ マイナ保険証の利用率が一定基準以上である
- 令和7年4月以降は最低でも15%(一部小児科は12%)以上が必要です。利用率は支払基金から通知される公式データで確認します。
- ☐ 院内の見やすい場所に必要な事項を掲示している
- 厚生労働省提供のポスターを活用するのが簡単です。
- ☐ (原則として)ウェブサイトに必要な事項を掲載している
- 【注意】令和7年5月31日までは経過措置がありますが、それ以降は対応が必要です(自院HPがない場合を除く)。
【加算対応のその先へ】日々の業務もDXで効率化しませんか? – AI活用「極 医療文書」のご紹介
ここまで、医療DX推進体制整備加算の届出チェックリストについて解説しました。オンライン資格確認や電子処方箋などの体制整備は、国が目指す質の高い医療提供の基盤となります。
しかし、先生方の日々の業務には、こうした制度対応以外にも効率化できる部分が多くあるのではないでしょうか?特に、紹介状をはじめとする医療文書の作成は、正確性が求められる一方で、多忙な診療の合間に行う必要があり、大きな負担となりがちです。
そこで注目したいのが、AIを活用した紹介状作成サポートツール**「極 医療文書」**です。
「極 医療文書」は、AIが紹介状のドラフトを迅速に作成することで、先生方の時間的負担を大幅に軽減することを目指したサービスです。これにより、先生は本来注力すべき診療や、オンライン資格確認等で得た診療情報を深く考察する時間をより多く確保できます。これは、単なる業務効率化に留まらず、医療DXが目指す**「質の高い医療の提供」にも直接繋がる**メリットと言えるでしょう。
さらに、「極 医療文書」は電子カルテとの連携は不要で、すぐに導入できる手軽さも魅力です。
「紹介状作成の手間を大幅に削減し、診療の質向上にも繋げたい」とお考えの先生は、ぜひ一度、その可能性をご検討ください。
届出は必要?不要?手続きステップ
では、本題に戻り、医療DX推進体制整備加算の届出について説明を続けます。この届出が必要かどうかは状況によります。
【届出が必要なケース】
- 新規にこの加算の算定を始める場合
- (既に加算4~6を算定中)電子処方箋体制を整備し、より点数の高い加算1~3を算定したい場合
- 小児科が利用率の特例(12%基準)を適用して加算3または6を算定する場合(令和7年9月30日まで)
【届出(届出直し)が不要なケース】
- 既に届出済みで、マイナ保険証利用率の変動により算定区分が変わる場合(例: 加算6→加算5)
- 既に届出済みで、電子処方箋未導入の区分(加算4~6)を引き続き算定する場合
【手続きのステップ】
- 必要書類の準備:
- 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)
- 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式1の6)
- ※様式は必ず管轄の地方厚生(支)局HPから最新版をダウンロードしてください。
- 様式1の6の記入:
- チェックリスト形式で、満たしている基準に「✓」を記入します。
- 経過措置が終了した項目(電子処方箋)、これから終了する項目(電子カルテ情報共有サービス、Webサイト掲載)の扱いに注意してください。最新の様式と記入例を確認しましょう。
- 提出:
- クリニックの所在地を管轄する**地方厚生(支)局の事務所(担当部署を確認)**へ、郵送または持参で提出します(1部)。
- 提出した届出書のコピーは必ず保管してください。
【提出時期と算定開始】
- 原則、月末までに受理されれば翌月1日から、月初開庁日に受理されればその月の1日から算定可能になります。
押さえておきたい運用ポイント
届出後も注意が必要です。
- マイナ保険証利用率の確認: 支払基金から通知される公式データを定期的に確認しましょう。院内集計ではなく、通知された数値に基づき、算定可能な最も有利な期間(直近3~5ヶ月で最高値など)の実績を適用します。
- 基準を満たせなくなったら?:
- 利用率が基準未満になった場合:その期間は加算を算定できませんが、辞退届は不要です。請求しない対応となります。
- その他の基準(システム不備、掲示中止など)を満たせなくなった場合:原則として辞退届の提出が必要になることがあります。管轄の厚生局にご確認ください。
- 監査対策: 施設基準の遵守(特に診察室での活用状況、掲示)、請求の正確性(月1回初診時、正しい利用率に基づく区分)がチェックされます。届出書類の控え、システム関連書類、利用率通知、掲示物の記録などをしっかり保管しておくことが重要です。
まとめ:加算取得と医療DX推進のために
医療DX推進体制整備加算は、今後のクリニック運営に欠かせない要素です。
- 自院の状況を確認し、未対応の基準(特に電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス)への対応計画を立てましょう。
- 必要に応じて、最新の様式で正しく届出を行いましょう。
- マイナ保険証利用率のモニタリングや掲示など、運用ルールを守りましょう。
- 厚生労働省や医師会、地方厚生局などの最新情報を継続的にチェックしましょう。
この加算への対応は、単なる義務ではなく、業務効率化や医療の質向上にもつながるチャンスです。ぜひ前向きに取り組んでいきましょう。
【最後に】日々の業務をもっと効率的に – AI紹介状作成サポート「極 医療文書」
医療DX推進体制整備加算への対応とあわせて、日々の文書作成業務も見直してみませんか?
AIが紹介状のドラフト作成をサポートする**「極 医療文書」**なら、先生方の貴重な時間を節約し、より患者さんに向き合う時間を増やすお手伝いができます。電子カルテ連携も不要で、手軽に始められます。
ご興味のある先生は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。