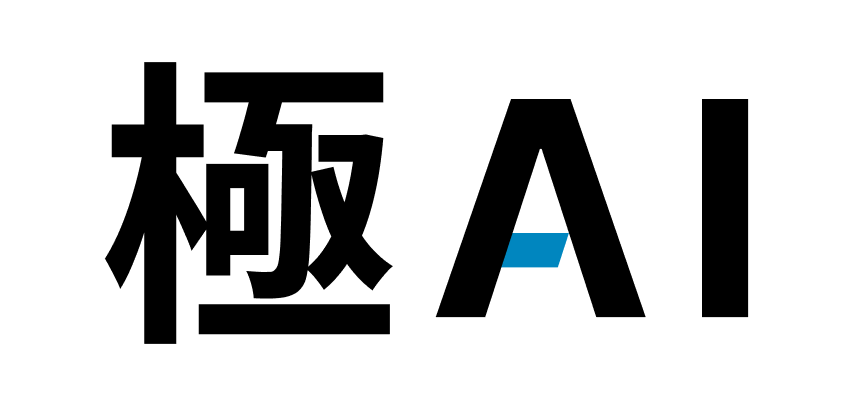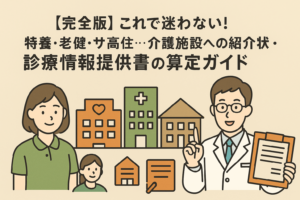【完全ガイド】連携強化診療情報提供料|算定要件5ステップ解説&診療情報提供料(I)との違いを徹底比較
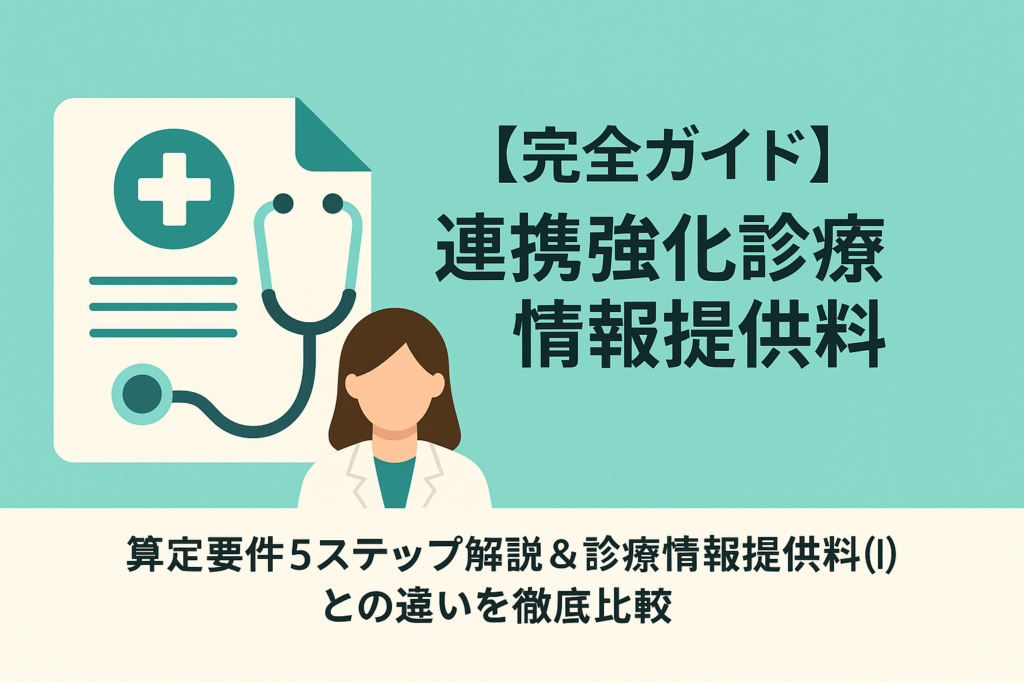
クリニックを開業・運営されている先生方にとって、日々の診療に加え、診療報酬に関する正確な知識は安定経営のために不可欠です。特に、医療機関間の連携を評価する項目は、地域医療への貢献とクリニックの収益の両面で重要性を増しています。
今回は、令和4年度改定で新設(旧 診療情報提供料(III)から改組)され、多くの先生方が算定要件や「診療情報提供料(I)(B009)」との違いについて疑問を持たれる「連携強化診療情報提供料(B011)」について、算定のポイントや注意点を分かりやすく、そして実践的に解説します。
連携強化診療情報提供料(B011)とは?
まず、連携強化診療情報提供料(B011)がどのようなものか、基本を押さえましょう。
- 定義: 他の医療機関から紹介された患者さんについて、その紹介元の医療機関からの「求め」に応じて、患者さんの「同意」を得た上で、診療状況を示す「文書」を提供した場合に算定できる医学管理料です。
- 点数: 150点
- 目的: 紹介して終わりではなく、紹介先の医療機関(先生のクリニック)から紹介元の医療機関へ、その後の患者さんの状況をフィードバックするという「双方向の情報連携」を評価し、促進することを目的としています。これにより、かかりつけ医と専門医療機関等が連携し、切れ目のない質の高い医療を地域で提供することを目指しています。
【重要】連携強化診療情報提供料を算定するための5つのステップ
連携強化診療情報提供料(B011)を算定するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。以下の5つのステップで確認していきましょう。
Step 1: 紹介元からの「求め」を確認する
- 算定の大前提として、患者さんを紹介した元の医療機関から「診療情報の提供をお願いします」という依頼(求め)が必要です。
- ポイント: この「求め」は、必ずしも文書である必要はなく、電話等による口頭での依頼でもOKとされています(厚生労働省 疑義解釈より)。
- 注意点: 口頭依頼の場合は、算定の根拠を残すため、「いつ、どの医療機関の、誰から、どんな依頼があったか」を必ず診療録に記録しましょう。文書で依頼を受けた場合は、その文書を診療録に添付すれば大丈夫です。記録がないと、審査で認められない可能性があります。
Step 2: 患者さんの「同意」を得る
- 患者さんの大切な診療情報を他の医療機関に提供するため、必ず患者さん本人の同意を得る必要があります。
- ポイント: 同意を得る際には、なぜ情報提供が必要なのか、どのような情報を提供するのかを説明しましょう。
- 注意点: 同意を得た旨(例:「〇〇病院への診療情報提供について説明し、同意を得た」など)も、忘れずに診療録に記載してください。
Step 3: 「診療状況を示す文書」を作成・提供する
- 紹介元の医療機関に対して、患者さんの具体的な診療状況がわかる**文書を作成し、提供(郵送や患者さん経由で交付など)**する必要があります。
- 記載すべき主な内容:
- 患者さんの氏名、生年月日、連絡先
- 情報提供先の医療機関名(=紹介元)
- 診療の方針、指導内容、検査結果、投薬内容など、具体的な診療状況
- 情報を提供する医療機関名(=自院)と担当医師名
- ポイント: 特定の様式は定められていませんが、診療情報提供料(I)(B009)で使う様式(別紙様式14の2や14の3)などで十分でしょう。
- 注意点: 提供した文書の写しは、必ず診療録に添付して保管しましょう。また単なるお礼状や形式的な返事(例:「ご紹介ありがとうございます」のみ)では算定できません。
【ちょっと一息】とはいえ、日々の忙しい診療の中で、これらの要件を満たした質の高い診療情報提供文書を毎回作成するのは、なかなか時間がかかり骨の折れる作業ですよね。特に、記載すべき情報が多くなるほど、抜け漏れがないか、分かりやすく伝わるかなど、気を遣う点も増えてきます。
実は最近、こうした文書作成の負担を軽減するために、AIを活用する動きも出てきています。例えば「極 医療文書」のようなツールは、必要な情報を基にAIが文書のドラフトを自動生成してくれるため、作成時間を大幅に短縮できる可能性があります。
電子カルテとの連携も不要で手軽に試せるので、「文書作成をもっと効率化したい」とお考えの先生は、一度情報収集してみるのも良いかもしれませんね。
Step 4: 算定頻度とタイミングを確認する
- 算定頻度: 原則として、情報を提供する先の医療機関(=紹介元)ごとに、患者さん1人につき「月1回」まで算定できます。(※後述する妊娠中の患者さんに関するケースでは例外あり)
- これは、以前の「3月に1回」から変更された点で、より密な連携を促す意図があります。
- 算定タイミング:
- 原則として、初診料を算定する日には算定できません。
- 例外: 初診を行った日に、次回の受診日の予約を行った場合は、初診日でも算定可能です。この場合は、予約日を診療録に記載する必要があります。
Step 5: 算定パターンと施設基準を確認する
ここが少し複雑ですが、B011を算定できるのは、紹介元・紹介先(自院)・患者さんが特定の組み合わせ(算定パターン)に合致する場合に限られます。そして、そのパターンに応じて自院だけでなく「紹介元」の医療機関も特定の施設基準を満たしているかを確認する必要があります。これがB009との大きな違いです。
主な算定パターン(令和6年度診療報酬点数表「注」より):
パターン1:『かかりつけ医機能を持つ医療機関』が関わる連携
- どんな連携?
- 地域で日常的な診療や健康管理を担う「かかりつけ医機能を持つ医療機関(※1)」から紹介された患者さんについて、自院(紹介先)が情報提供(返信)する場合。
- 自院(情報提供する側)の基準:
- 敷地内禁煙であること。(これは基準を満たしていればよく、特別な届出は不要です)
- 紹介元(紹介してくれた側)の基準:
- 「かかりつけ医機能に係る施設基準(※1)」を満たしていること。(例:機能強化加算、地域包括診療料・加算などを届け出ている医療機関)
- ★重要:紹介元がこの基準を満たしているか、確認が必要です!(確認方法は後述)
パターン2:自院が『紹介受診重点医療機関』の場合の連携
- どんな連携?
- 専門的な外来医療を中心に担う「紹介受診重点医療機関(※2)」として都道府県から公表されている自院が、地域の診療所や中小病院(許可病床200床未満)から紹介された患者さんについて、紹介元へ情報提供(返信)する場合。国の進める外来機能分化・連携強化の核となるパターンです。
- 自院(情報提供する側)の基準:
- 「紹介受診重点医療機関」として公表されており、かつ敷地内禁煙であること。
- 紹介元(紹介してくれた側)の基準:
- 許可病床数が200床未満の病院又は診療所であること。
- ★重要:紹介元がこの基準を満たしているか、確認が必要です!
パターン3:自院が『かかりつけ医機能を持つ医療機関』の場合の連携
- どんな連携?
- 自院が「かかりつけ医機能を持つ医療機関(※1)」であり、他の医療機関(例えば、専門病院など)から紹介された患者さんについて、その紹介元からの求めに応じて情報提供する場合。(逆紹介後のフォローアップ情報提供などが考えられます)
- 自院(情報提供する側)の基準:
- 「かかりつけ医機能に係る施設基準(※1)」を満たしていること。
- 紹介元(情報を求めてきた側)の基準:
- 特に定めはありません(他の保険医療機関であればOK)。
パターン4:自院が『難病・てんかんの拠点病院』の場合の連携
- どんな連携?
- 自院が「難病診療連携拠点病院」や「てんかん支援拠点病院」など(※3)であり、他の医療機関から紹介された指定難病やてんかんの患者さん(疑い含む)について、紹介元へ専門的な診療状況を情報提供する場合。
- 自院(情報提供する側)の基準:
- 難病やてんかんに係る拠点病院としての施設基準(※3)を満たしていること。
- 紹介元(情報を求めてきた側)の基準:
- 特に定めはありません。
- 対象患者:
- 指定難病の患者さん、または、てんかん(疑い含む)の患者さん。
パターン5:『妊娠中の患者さん』に関する連携
- どんな連携?
- 他の医療機関から紹介された妊娠中の患者さんについて、自院(紹介先)が紹介元へ情報提供する場合。産科・産婦人科間の連携(産産連携)や、産科と他科との連携などが想定されます。
- 自院(情報提供する側)の基準:
- 敷地内禁煙であること。
- 紹介元(情報を求めてきた側)の基準:
- 特に定めはありません。
- 対象患者:
- 妊娠中の患者さん。
- 算定頻度の特例(注意!):
- このパターンは、原則として**「3月に1回」**の算定です。
- ただし、 医師が「頻回の情報提供が必要」と判断し、以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、**「月1回」**算定できます。(通知(6))
- 自院が「産科・産婦人科を標榜」し「特定の産科関連施設基準(※4)」を満たしており、紹介元(産科以外も可)へ情報提供する場合。
- 紹介元が「産科・産婦人科を標榜」し「特定の産科関連施設基準(※4)」を満たしており、自院(産科以外も可)がその紹介元へ情報提供する場合。
【用語補足】
- ※1 かかりつけ医機能に係る施設基準: 機能強化加算、地域包括診療料、地域包括診療加算、在宅時医学総合管理料などの届出を行っていることなどが該当します。
- ※2 紹介受診重点医療機関: 手術・処置や化学療法等の専門的な外来医療を中心に提供する病院として、都道府県が地域の協議を経て公表した医療機関です。自院が該当するかは、都道府県の公表情報を確認してください。
- ※3 難病・てんかんに係る拠点病院としての施設基準: 都道府県からの指定や、難病法等に基づく要件を満たしていることなどが該当します。
- ※4 特定の産科関連施設基準: 妊娠中の患者さんの診療について十分な体制が整備されていることなど、別に厚生労働大臣が定める基準です。
更なる詳細を確認されたい方は、厚生労働省の公式資料をご確認ください。
診療情報提供料(I)との違いを徹底比較
B011とよく似た名称の「診療情報提供料(I)(B009)」がありますが、目的や算定要件が大きく異なります。違いをしっかり理解しましょう。
| 項目 | 連携強化診療情報提供料 (B011) | 診療情報提供料(I) (B009) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 紹介後の連携強化 (紹介先→紹介元への返信) | 患者紹介 (紹介元→紹介先・他機関への情報提供) |
| 算定トリガー | 紹介元からの「求め」、患者同意 | 紹介の必要性判断、患者同意 |
| 情報の流れ | 紹介先 → 紹介元 | 紹介元 → 紹介先/情報提供先 |
| 算定主体 | 紹介先の医療機関(情報提供側) | 紹介元の医療機関(情報提供側) |
| 基本点数 | 150点 | 250点 |
| 主な加算 | なし | 多数あり(退院時、認知症、歯科連携、検査・画像情報提供 等) |
| 算定頻度 | 月1回/提供先ごと(妊娠中は例外あり) | 月1回/紹介先・提供先ごと |
| 施設基準(基本算定) | 算定医療機関・紹介元双方に要件あり (パターンによる) | 原則不要(ただし加算算定には必要な場合あり) |
| 主な対象場面 | 特定連携パターンでの紹介後の返信 | 広範な紹介・情報提供場面(専門医紹介、医療介護連携 等) |
【最重要】同月算定不可ルール
- 同一の患者さんについて、同一の医療機関に対して、同じ月にB009とB011の両方を算定することはできません。
- 例:
- 自院が患者AさんをB病院に紹介し、B009(250点)を算定した月には、たとえ同月内にB病院から「患者Aさんの状況を教えて」と求められて情報提供(B011に該当する行為)しても、B011(150点)は算定できません。
- 逆も同様です。B病院から紹介された患者Aさんについて、B病院からの求めに応じてB011を算定した月には、たとえ別の理由で自院からB病院へ患者Aさんを紹介しても、B009は算定できません。
- 注意点: レセプト請求時には、この「同月算定不可」のルールに抵触していないか、必ず確認しましょう。
連携強化診療情報提供料の注意点とよくある疑問
- 特別の関係: 情報提供先(紹介元)が、自院と親子関係や同一法人など「特別の関係」にある場合は算定できません。
- 歯科との関係: 歯科の「診療情報等連携共有料2」を算定した月は、同一の医療機関への文書提供の場合、B011は算定できません。
- 依頼から時間が空いた場合: 依頼を受けて文書を作成していても、患者さんがなかなか来院せず、算定までに時間が空いてしまうこともあり得ます。B011は診療に基づき算定するため、実際に患者さんが来院し診療を行った日に算定します。ただし、依頼から長期間経過している場合は、情報提供の適時性が問われる可能性もゼロではありません。可能であれば次回の来院時など、速やかに情報提供・算定するのが望ましいでしょう。あまりに時間が空いた場合は、念のため紹介元に情報提供の要否を再確認することも検討しましょう。
まとめ
連携強化診療情報提供料(B011)は、紹介患者さんに関する情報を紹介元へフィードバックするという、これからの地域医療連携において非常に重要な役割を担う診療報酬項目です。
- 紹介元からの「求め」
- 患者さんの「同意」
- 「診療状況を示す文書」の作成・提供
- 自院と「紹介元」の施設基準の確認
- 診療情報提供料(I)との違いの理解と「同月算定不可」ルールの遵守
これらのキーポイントを押さえ、適切な算定を心がけることが、質の高い医療連携の実践と、クリニックの安定経営につながります。
紹介状作成、AIでもっと楽にしませんか?
今回解説した連携強化診療情報提供料(B011)をはじめ、医療機関同士の情報共有はますます重要になっています。こうした連携をよりスムーズに、そして効率的に行うための一つの選択肢として、AIによる文書作成支援ツールも登場しています。
例えば「極 医療文書」は、紹介状や診療情報提供書などの作成をAIがサポートし、先生方の時間創出や、記載内容の質の担保に貢献することを目指しています。ご興味のある先生は、ぜひ一度、以下のリンクから詳細をご確認ください。
この記事が、先生方の日常診療におけるB011の理解と活用の一助となれば幸いです。