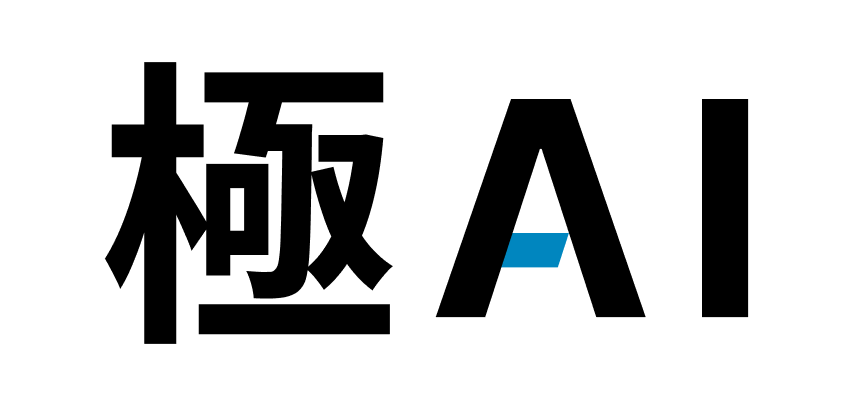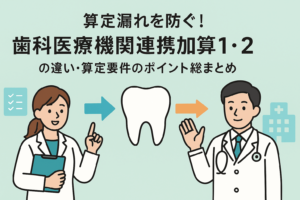【2025年4月改訂対応】在宅医療DX情報活用加算 完全ガイド:算定要件と実践ステップ

2024年6月に新設され、そして 2025年4月1日から早くも内容が改定された「在宅医療DX情報活用加算」。在宅医療の現場でもDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の波が本格化しています。
「具体的に何をすれば算定できるの?」 「2025年4月から何が変わった?」 「うちのクリニックでも取り組むべき?」
このような疑問をお持ちの先生方のために、本記事では「在宅医療DX情報活用加算」について、算定のポイントから具体的な手順、注意点まで、現場で役立つ実践的な情報 を分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 在宅医療DX情報活用加算の目的と概要
- 最新(2025年4月1日施行)の算定要件と点数(加算1・加算2の違い)
- クリアすべき施設基準(特に重要なポイントと経過措置)
- 算定に向けた具体的な導入ステップと運用フロー
- レセプト記載や他の加算との関係性における注意点
単なる点数加算だけでなく、今後のクリニック運営や地域連携においても重要となる医療DXへの対応。ぜひ本記事を参考に、算定に向けた準備を進めていただければ幸いです。
1. 在宅医療DX情報活用加算とは? ~基本を押さえる~
1.1. 目的:オンライン資格確認情報を診療に活かす
この加算は、オンライン資格確認システム等を通じて得られる患者さんの診療情報や薬剤情報を、先生方が計画的な医学管理(在宅での診療計画の作成・実行など)に活用することを評価するものです。
単に情報を取得するだけでなく、その情報を基に、より質の高い、個別化された在宅医療を提供することが目的とされています。これは、今後の医療提供体制において、デジタル技術の活用が標準的な要件となりつつあることの表れでもあります。
1.2. 対象となる診療行為と患者
以下のいずれかの在宅医療関連の診療料を算定している患者さんに対して、訪問診療を行った場合に算定可能です。
- 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1
- 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2
- 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
- 在宅がん医療総合診療料
1.3. 算定点数(2025年4月1日~)
2025年4月1日より、電子処方箋への対応状況によって評価が2段階になりました。
- 在宅医療DX情報活用加算1:11点
- 電子処方箋を発行する体制(※後述)が整っている場合に算定。
- 在宅医療DX情報活用加算2:9点
- 電子処方箋を発行する体制が整っていない場合に算定。
いずれも、対象患者1人につき月1回に限り算定できます。
2. 算定のための重要要件 ~「何をすれば良いか」を具体的に~
加算算定の核心は、オンライン資格確認等で得た情報を「踏まえ」、「計画的な医学管理」の下で訪問診療を行うことです。
2.1. 「計画的な医学管理」とは?
厚生労働省から明確な定義は示されていませんが、趣旨としては以下のプロセスに取得した情報を能動的に組み込むことと考えられます。
- 診療計画の策定・見直し: 取得した情報(過去の受診歴、処方薬、健診結果など)を基に、個々の患者さんに最適化された診療計画を立てる、または修正する。
- 訪問診療時の判断: 訪問時の診断、治療方針の決定、薬剤選択などに取得情報を反映させる。
- 患者指導: 取得情報を踏まえて、生活指導や服薬指導などをより具体的に行う。
【ポイント】 単に情報を「見た」だけでは不十分です。その情報が先生の判断や管理計画に実質的な影響を与え、診療プロセスに統合されていることが重要です。後から検証できるよう、どのような情報をどう評価し、どう計画に反映したかを診療録(カルテ)に記録しておくことが、実務上強く推奨されます。
とはいえ、日々の診療の中でカルテ記録はもちろん、他の医療機関への紹介状など、文書作成業務に多くの時間を取られている先生も少なくないのではないでしょうか。こうした日々の文書作成業務の効率化も、クリニック運営における重要なテーマです。 最近では、AI技術を活用して紹介状作成をサポートするサービスも登場しています。例えば「極 医療文書」は、AIが紹介状の下書きをスピーディーに作成し、先生の負担軽減を目指すツールです。電子カルテ連携も不要で手軽に始められます。ご興味があれば、ぜひ以下より詳細をご覧になってみてください。
2.2. 情報「活用」の具体的なステップ
こちらも明確な定義はありませんが、「取得した情報を踏まえて計画的な医学管理を行う」という要件から、取得した情報を実際の診療行為や管理計画に反映させる仕組みが求められます。
具体的には、「居宅同意取得型」オンライン資格確認システム等で取得した情報を、先生が電子カルテ等を通じて容易に閲覧し、診療計画作成時などに参照・活用できる体制が整備されている必要があります。
2.3. 算定頻度
対象患者1人につき、月に1回限り算定可能です。
2.4. 初回訪問診療での算定は可能か?
可能です。 ただし、初回の訪問診療を行う「前」にオンライン資格確認で患者情報を取得し、その情報を「初回訪問時」の診療計画作成や方針決定に活用することが条件です。 つまり、新規患者さんを受け入れる際に、訪問前に情報取得・分析を行い、それに基づいた初回訪問計画を立てるというプロアクティブな業務フローが必要です。
2.5. 算定できないケース:併算定不可ルールに注意!
以下の加算を同月に算定している場合、在宅医療DX情報活用加算は算定できません。
| 併算定が認められない主な加算 | 対象診療報酬項目 |
|---|---|
| 医療情報取得加算 | 初診料、再診料、外来診療料 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 初診料 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 訪問看護療養費、精神科訪問看護・指導料 |
【重要注意点】 在宅がん医療総合診療料に対して本加算を算定した場合、同じ月に在宅患者訪問診療料(ⅠまたはⅡ)に対して本加算を重ねて算定することはできません。
3. 必須となる施設基準 ~クリアすべきハードル
本加算を算定するには、以下の施設基準を満たし、地方厚生(支)局長等に届け出る必要があります。
3.1. 基本インフラ:オンライン請求&オンライン資格確認
- オンライン請求: 電子レセプト請求を行っていること。
- オンライン資格確認体制: マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制(顔認証付きカードリーダー等)が整備・運用されていること。
3.2. 在宅医療特有の要件:居宅同意取得型システムの整備と「活用」
- 居宅同意取得型オンライン資格確認システム: 医師等が患者宅等で患者の診療・薬剤情報等を取得し、それを診療に「活用」できる体制が必要です。
- 運用イメージ:
- 医療機関が用意したモバイル端末(スマホ/タブレット等)を使用。
- 訪問先で患者さんにマイナカードを提示してもらい、モバイル端末で読み取り、暗証番号入力等で本人確認と同意を得る。
- 同意後、院内の端末等から患者情報を閲覧し、診療計画等に活用する。(※訪問先の端末から直接閲覧できない情報もあるため、院内での事前/事後確認が必要な場合あり)
- オンライン資格確認システムの管理画面で**「訪問診療等機能」を有効化**し、同意取得用Webサイト(マイナ在宅受付Web)のURL/QRコードを生成・利用する。
- 【ポイント】 単に機器を導入するだけでなく、訪問診療ワークフローへの組み込み(同意取得手順、情報確認タイミング)、スタッフへの操作・セキュリティ教育、厳格なセキュリティ管理(OS更新、ウイルス対策、パスワード設定等)が不可欠です。
- 運用イメージ:
3.3. 電子処方箋発行体制【加算1/加算2の分岐点!】
- 要件: 電磁的記録をもって作成された処方箋(電子処方箋)を発行する体制を有していること。具体的には、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制が求められます。
- 現在 (2025年4月以降):
- この体制が整っている → 在宅医療DX情報活用加算1(11点)の算定要件
- この体制が整っていない → 在宅医療DX情報活用加算2(9点)を算定
3.4. 電子カルテ情報共有サービス活用体制
- 要件: 国が整備を進める「電子カルテ情報共有サービス」(医療機関間で患者情報を安全に共有する全国ネットワーク)を活用できる体制を有していること。
- 経過措置: 2025年9月30日までは、体制が整備されていなくても基準を満たすとみなされます。(サービス自体は2025年4月に開始予定とされています)
- 【ポイント】 経過措置期間中に情報収集し、自院システムとの連携可能性や業務フローへの影響を検討しておくことが望ましいでしょう。
3.5. 院内及びウェブサイトへの掲示義務
以下の内容を院内の見やすい場所(受付、待合室など)に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載する必要があります。
- 医療DX推進の体制に関する事項(例:オンライン資格確認を行う体制を有していること)
- 質の高い診療のため、オンライン資格確認等で得られる情報を取得・活用して診療を行っている旨
- ウェブサイト掲載の経過措置: 2025年5月31日まで猶予期間があります。
【施設基準まとめ】
| 施設基準項目 | 要件概要 | 経過措置終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| オンライン請求 | 電子レセプト請求 | なし | |
| オンライン資格確認体制 | マイナ保険証対応体制 | なし | |
| 居宅同意取得型システム活用体制 | 患者宅等で情報取得&診療に活用できる体制 | なし | |
| 電子処方箋発行体制 | 電子処方箋を発行・登録できる体制 | 終了済 | 加算1(11点)算定の必須要件 |
| 電子カルテ情報共有サービス活用体制 | 国の共有サービスを活用できる体制 | 2025年9月30日 | |
| 院内掲示 | DX推進体制、情報活用方針等 | なし | |
| Webサイト掲示 | 院内掲示と同様の内容 | 2025年5月31日 | 原則として掲載義務あり |
4.【最重要】2025年4月改定:加算1 vs 加算2 と「届出直し」
2025年4月1日から施行された改定内容のポイントを整理します。
4.1. なぜ2段階評価になったのか?
国の電子処方箋普及促進の意向が背景にあります。対応医療機関を高く評価(加算1: 11点)し、未対応でも一定の評価(加算2: 9点)を残すことで、段階的な導入を促す狙いです。
4.2. 点数と要件の違い(再掲)
- 加算1 (11点): 電子処方箋発行体制が必須。その他の施設基準も満たす必要あり。
- 加算2 (9点): 電子処方箋発行体制は不要。その他の施設基準は満たす必要あり。
4.3. 届出に関する重要事項:「届出直し」は必要?
- 加算2 (9点) を算定する場合:
- 2025年3月31日時点で旧「在宅医療DX情報活用加算」の届出があり、引き続き加算2の施設基準を満たしていれば、新たな届出(届出直し)は不要です。
- 加算1 (11点) を算定する場合:
- たとえ旧加算の届出があっても、加算1を算定するには必ず新たな様式での届出直しが必要です。
- 電子処方箋発行体制を整備した上で、地方厚生(支)局長等へ届け出る必要があります。
【ポイント】 加算1を目指す場合、技術的な基準充足だけでなく、行政手続きとしての届出が不可欠です。
5. 実践!クリニック導入ガイド ~算定に向けたステップと運用~
5.1. 導入準備:チェックリスト
- □ 基盤確認: オンライン請求、オンライン資格確認システム(院内用)は稼働中か?
- □ 居宅同意取得型対応:
- モバイル端末(訪問用)の準備
- システム管理画面で「訪問診療等機能」を有効化
- 同意取得用Webサイト(マイナ在宅受付Web)のURL/QRコード準備
- 訪問スタッフへの操作・セキュリティ教育計画
- □ 電子処方箋対応 (加算1を目指す場合):
- 医師のHPKIカード取得
- 対応システムの導入・改修(ベンダー相談、見積もり、発注)
- システム導入・設定完了
- 安全管理措置の確認・報告
- □ 電子カルテ情報共有サービス対応:
- 情報収集開始 (経過措置: 2025年9月末まで)
- 自院システムとの連携、参加準備検討
- □ 掲示物:
- 院内掲示物の作成・設置
- ウェブサイトへの掲載準備 (経過措置: 2025年5月末まで)
- □ 地方厚生局への届出:
- 必要な施設基準を満たした上で、届出様式を提出
- 加算1算定希望の場合、届出直しを忘れずに!
5.2. 居宅同意取得型の運用ワークフロー(例)
- 訪問前: 担当者がモバイル端末、マイナ在宅受付Webアクセス手段を準備。
- 訪問先: 患者/家族にマイナカードを用意してもらう。
- 同意取得:
- モバイル端末でマイナ在宅受付Webを開き、患者に説明・同意確認。
- 患者が暗証番号(4桁)を入力し、カード読み取り。(入力ミス3回でロック注意!)
- ※暗証番号入力が困難な場合、顔写真確認による方法も可。
- 情報活用: 同意後、院内端末等で診療・薬剤情報を照会・閲覧。診療計画等に活用。
- 記録: 活用した情報をカルテに記録。
【運用上の留意点】 訪問担当スタッフへの十分なトレーニング(説明、操作、トラブル対応、プライバシー配慮)が成功の鍵です。
5.3. マイナンバーカード利用率との関連
本加算の施設基準にマイナ保険証の利用率目標は直接含まれていません。 しかし、併算定不可である「医療DX推進体制整備加算」では利用率が点数を左右します。
両加算はDX推進という目標を共有し、オンライン資格確認体制という基盤も同じです。医療DX推進体制整備加算のためにマイナ保険証利用促進に取り組むことは、結果的に本加算の運用円滑化にも繋がります。間接的に利用促進への取り組みが求められている状況と言えるでしょう。
6. まとめと今後の展望
6.1. 本加算のポイント再確認
- オンライン資格確認情報を計画的な医学管理に活用することを評価。
- 2025年4月から電子処方箋対応有無で加算1(11点)/加算2(9点)に分化。
- 算定には施設基準充足と届出(加算1は届出直し必須)が必要。
- 「居宅同意取得型」の運用体制構築とカルテへの記録が重要。
- 医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算等とは併算定不可。
6.2. クリニックが取るべきアクション
- 現状把握と計画: 自院の施設基準充足度を確認。特に電子カルテ情報共有サービス(2025/9末まで)、Web掲示(2025/5末まで)の経過措置期限を見据え計画を。
- 加算1/加算2の選択と対応: 電子処方箋導入を検討。加算1を目指すならシステム導入と届出直しを確実に。
- 運用体制構築: 居宅同意取得型の運用マニュアル作成とスタッフ研修実施。
- 記録の徹底: 「情報をどう活用したか」をカルテに具体的に記載する習慣づけ。
- 継続的な情報収集: 厚労省、医師会等の最新情報を常にチェック。
在宅医療DX情報活用加算への対応は、目先の収益だけでなく、クリニックの将来性を左右する重要な取り組みです。医療DXの潮流に乗り遅れないためにも、計画的な準備と実践を進めていきましょう。
【終わりに】文書作成の効率化も、クリニックDXの重要な一歩です
さて、医療DXは情報活用だけでなく、日々の業務プロセス全体の効率化も重要なテーマです。特に、診療情報提供書(紹介状)の作成は、先生方の貴重な時間を少なからず要する業務の一つではないでしょうか。
もし「紹介状作成をもっとスムーズにできたら…」「文書業務の負担を少しでも減らしたい」と感じていらっしゃるなら、AIがその作成をサポートするツール「極 医療文書」をチェックしてみませんか?
AIが紹介状のドラフト作成をアシストし、先生の業務負担を軽減します。電子カルテとの連携も不要なため、手軽に導入をご検討いただけます。 詳しくは、こちらのページをご覧ください。