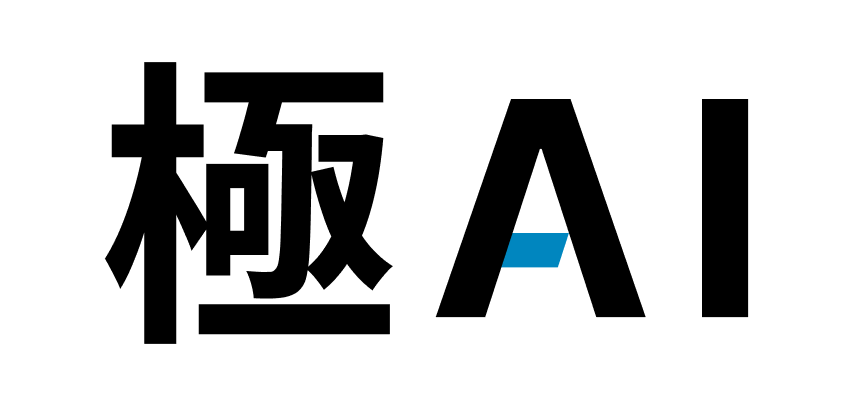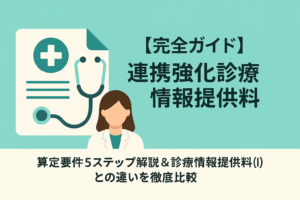【2025年最新】認知症専門医療機関紹介加算 – 算定要件・診療報酬請求の注意点を徹底解説

クリニックを開業されている先生方にとって、高齢化に伴い認知症の患者さんやその疑いのある方に接する機会はますます増えていることと存じます。認知症は早期発見と適切な初期対応が非常に重要であり、地域で患者さんに最も身近なかかりつけ医の役割はますます大きくなっています。
そのような中、患者さんを専門医療機関へ紹介する際の評価である「認知症専門医療機関紹介加算」について、「通常の診療情報提供料(I)と何が違うの?」「どんな時に算定できるの?」といった疑問をお持ちの先生方も多いのではないでしょうか。
この記事では、多忙な先生方のために、「認知症専門医療機関紹介加算」について、その算定要件や対象となる専門医療機関、診療情報提供料(I)との違い、そして実務上のポイントまで、分かりやすく、かつ実践的に解説します。
1. まずは基本から:診療情報提供料(I)(B009)とは?
「認知症専門医療機関紹介加算」を理解するために、まずは土台となる診療情報提供料(I)の基本を簡単にまとめます。
- 目的: 他の医療機関や介護施設等との連携を評価し、患者さんに継続的で質の高い医療を提供する。
- 点数: 250点
- 算定できるケース:
- 患者さんの診療に基づき、他の保険医療機関や介護施設等での診療・サービス提供が必要と判断した場合。
- 患者さん本人またはご家族等の同意を得ていること。
- 診療状況を記載した文書(診療情報提供書)を作成・添付して紹介すること。
- 紹介先の例: 他の病院・クリニック、市町村、指定居宅介護支援事業者、介護老人保健施設、介護医療院など。
- 算定回数: 紹介先の医療機関ごとに、患者さん1人につき月1回まで。
この診療情報提供料(I)には、特定の条件を満たす場合に点数を上乗せできる「加算」がいくつかあり、「認知症専門医療機関紹介加算」もその一つです。
2. 本題:「認知症専門医療機関紹介加算」を徹底解説
ここからが本題の「認知症専門医療機関紹介加算」です。通常の診療情報提供料(I)と何が違うのか、詳しく見ていきましょう。
目的と意義
この加算は、かかりつけ医である先生方が**「認知症の疑い」に早期に気づき、鑑別診断や初期対応が可能な「専門医療機関」**へ適切に紹介することを後押しするために設けられています。認知症の早期診断・早期対応は、患者さんとご家族のその後の生活の質(QOL)を大きく左右します。この加算は、その重要な入口となる「かかりつけ医による早期発見と専門医への橋渡し」を評価するものです。
診療情報提供料(I)との違い
通常の診療情報提供料(I)(250点)と比べて、以下の点が異なります。
| 項目 | 診療情報提供料(I)(基本) | 認知症専門医療機関紹介加算(注10) |
|---|---|---|
| 点数 | 250点 | +100点 (合計 350点) |
| 対象患者 | 特になし(紹介が必要な患者) | 「認知症の疑い」 のある患者 |
| 紹介先 | 他の医療機関、介護施設等 | 「専門医療機関」 (※後述) |
| 紹介目的 | 診療・サービス提供依頼 | 主に鑑別診断等の依頼 |
算定要件(これを満たせば算定OK!)
以下のすべてを満たす場合に、診療情報提供料(I)の250点に100点を加算できます。
- 対象患者: 先生が診察の結果、「認知症の疑いがある」と判断した患者さんであること。(※確定診断後の紹介は対象外)
- 紹介先: 厚生労働省が定める機能を持つ「専門医療機関」(詳細は次章)へ紹介すること。(※都道府県等が指定する認知症疾患医療センターへの紹介も対象です)
- 手続き:
- 患者さん本人またはご家族等の同意を得ること。
- 患者さんの診療状況を記載した診療情報提供書を作成・添付すること。
算定できないケース(要注意!)
原則として、以下の施設に入所または入居している患者さんへの紹介では、この加算は算定できません。
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護老人福祉施設(特養)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(特定施設)
- 介護医療院 など
- 小規模多機能型居宅介護等の宿泊サービス利用中の患者
※これらの施設に入所中の方は、施設サービスや介護保険の枠組みで対応されるため、本加算の対象外となります。 ※自宅や一般の社会福祉施設等にお住まいの方、医療保険適用の一般病床等に入院中の方は算定対象です。
日々の業務の効率化を考える先生へ
さて、算定要件を満たすためには、適切な診療情報提供書の作成が不可欠です。特に認知症が疑われる患者さんの場合、これまでの経過やご家族からの情報、診察所見などを詳細に記載する必要があり、多忙な診療の合間を縫って作成するのは時間的な負担が大きいと感じる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
「診療情報提供書の作成が、もう少しスムーズになれば…」そんな声にお応えすべく、近年ではAI技術を活用して文書作成を支援するツールも開発されています。例えば、「極 医療文書」は、AIが紹介状のドラフト作成をサポートし、先生方の文書作成にかかる時間を大幅に短縮することを目指したサービスです。電子カルテとの連携も不要で、すぐに試せる手軽さも特徴です。ご興味があれば、一度情報収集してみてはいかがでしょうか。
3. 紹介先となる「専門医療機関」とは?
この加算を算定するには、紹介先が「専門医療機関」に該当する必要があります。
診療報酬上の定義
「専門医療機関」とは、特定の指定を受けていることではなく、以下の機能を持つ保険医療機関を指します。
- 認知症の鑑別診断
- 専門医療相談
- 合併症への対応
- 医療情報の提供
- かかりつけ医や介護サービス等との連携調整
実質的には、これらの機能を高いレベルで担っている認知症疾患医療センターや、大学病院、精神科病院、神経内科など、認知症の専門的な診療体制を持つ病院・診療所が主に想定されます。
代表例:認知症疾患医療センター
都道府県や指定都市が指定する、地域における認知症医療の中核拠点です。鑑別診断、初期対応、専門相談、地域連携などを担います。
- 種類: 基幹型、地域型、連携型 があり、機能や役割が異なりますが、どの類型への紹介でも加算は算定可能です。
- 探し方:
- 都道府県や市町村のホームページ(福祉保健分野のページなど)
- 地域医師会の情報
- 地域包括支援センターへの問い合わせ
- 紹介を検討している医療機関への直接確認
紹介したい医療機関がこれらの機能を持っているか、地域の認知症疾患医療センターはどこか、事前に確認しておくとスムーズです。
4. もう一つの加算:「連携」加算との違い
診療情報提供料(I)には、もう一つ認知症関連の「認知症専門医療機関連携加算」があります。これは紹介先の専門医療機関側が算定するものです。
- 紹介加算: かかりつけ医 ⇒ 専門医 (認知症疑い患者の紹介)【今回解説している加算:100点】
- 連携加算: 専門医 ⇒ かかりつけ医 (診断結果や治療計画等の情報提供)【専門医側が算定:50点】
この2つの加算は、かかりつけ医と専門医の「双方向の連携」を評価するセットのようなものです。先生方が紹介した患者さんについて、専門医からこの「連携加算」を伴う返書(診療情報提供書)を受け取ることが、その後の継続的なフォローアップに繋がります。
まとめ
「認知症専門医療機関紹介加算」は、通常の診療情報提供料(I)に100点を加算できる制度です。
- 対象: 認知症疑いの患者さん
- 紹介先: 鑑別診断等の機能を持つ専門医療機関(認知症疾患医療センター含む)
- 手続き: 同意を得て、診療情報提供書を添付
- 注意: 施設入所者などは原則対象外
この加算を正しく理解し活用することは、認知症の早期発見・早期対応という、患者さんにとって非常に重要なプロセスを後押しします。また、かかりつけ医としての専門性を発揮し、地域連携を推進する上で重要なツールとなります。
この記事が、先生方の日々の診療とクリニック運営の一助となれば幸いです。
紹介状作成の効率化で、診療にもっと時間を
本記事で解説したように、適切なタイミングでの専門医への紹介は非常に重要ですが、そのための診療情報提供書(紹介状)作成に多くの時間を要することも事実です。日々の診療に加え、文書作成業務の負担を少しでも軽減したいとお考えの先生もいらっしゃるかもしれません。
AIが紹介状のドラフト作成をアシストする「極 医療文書」は、そのような先生方の負担軽減を目指して開発されました。必要な情報を入力するだけで、AIがたたき台となる文章を生成。先生は内容の確認・修正に集中でき、文書作成時間を大幅に削減できる可能性があります。
ご多忙な先生が、より患者さんに向き合う時間を確保するための一助として、こうした新しいツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、以下のリンクからご覧いただけます。