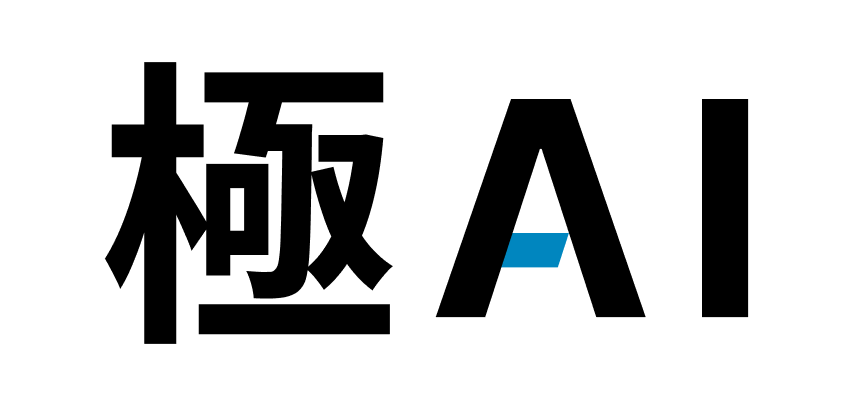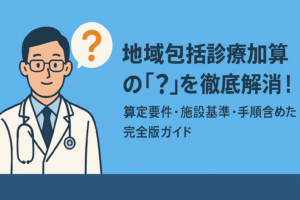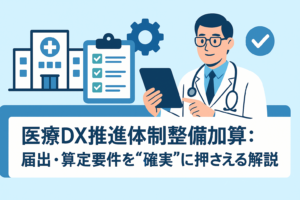【5分で分かる】医療文書の保存期間ルール|開業医のためのやさしい実務解説

クリニックを運営されている先生方にとって、日々の診療に加え、医療文書の適切な管理・保存は避けて通れない重要な業務です。しかし、「どの書類を、いつまで保存すればいいのか?」「電子保存のルールは?」など、複雑な規定に戸惑うこともあるのではないでしょうか。
医療文書の保存は、単に法律で定められているからというだけでなく、質の高い医療の提供、万が一のリスク管理、そしてクリニックの健全な運営に不可欠です。
この記事では、忙しい先生方のために、医療文書の保存に関する基本ルールと実務上のポイントを、分かりやすくシンプルに解説します。
これだけは押さえたい!主要な医療文書の保存期間
医療文書の保存期間は、主に医師法や保険診療に関わる「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当規則)などで定められています。特に重要なものをピックアップします。
- 診療録(カルテ): 完結の日から5年間
- 根拠:医師法第24条、療養担当規則第9条
- 処方箋の控え、エックス線写真、検査記録など、その他の保険診療に関する記録: 完結の日から3年間
- 根拠:療養担当規則第9条
ここで非常に重要なのが「完結の日」という考え方です。これは、単に文書を作成した日ではなく、「その患者さんの一連の診療が終了した日」を指します。例えば、
- 治癒した日
- 患者さんが亡くなられた日
- 治療が中断・中止された日
- 他の医療機関へ転院(紹介)した日
などが該当します。つまり、慢性疾患などで診療が継続している限り、「完結の日」は訪れず、たとえ古い記録であっても保存し続ける必要がある点に注意が必要です。
| 文書の種類 | 保存期間 | 起算日 | 主な根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5年間 | 完結の日 | 医師法、療養担当規則 |
| 処方箋(診療所控え) | 3年間 | 完結の日 | 療養担当規則 |
| エックス線写真 | 3年間 | 完結の日 | 療養担当規則 |
| 検査記録 | 3年間 | 完結の日 | 療養担当規則 |
| 手術記録 | 3年間 | 完結の日 | 療養担当規則 |
| 紹介状(控え・受領分) | 3年間 | 完結の日推奨 | 療養担当規則 |
| レセプト | 5年間(法定)/ 10年間(推奨) | 完結の日 | 療養担当規則/民法 |
※レセプトは法定5年ですが、保険者からの照会に対応するため、実務上10年保存が推奨されます。
紹介状(診療情報提供書)の扱いは?
紹介状の控え(自院が発行)や、受け取った紹介状(他院から受領)については、明確な法定保存期間が個別に定められているわけではありません。しかし、これらは患者さんの診療経過を把握する上で重要な記録です。
実務上は、療養担当規則の「その他の記録」に準じて、関連する診療の「完結の日」から3年間は保存するのが安全で合理的と考えられます。カルテと一緒に保管・管理するのが良いでしょう。
【ちょっと一息】その紹介状作成、もっと楽になりませんか?
さて、ここまで紹介状の「保管」について触れてきましたが、そもそもこの紹介状を「作成」する作業自体、先生方にとっては結構な時間と手間がかかるものではないでしょうか? 患者さん一人ひとりの状況に合わせて情報を整理し、分かりやすく文章にまとめるのは、忙しい診療の合間では特に大変です。
「この紹介状作成の時間をもっと短縮できれば、他の業務や患者さんとの時間にもっと集中できるのに…」と感じていらっしゃる先生も多いのではないでしょうか。
実は、そうした先生方の負担を軽減するために開発されたのが、AIを活用した紹介状作成サポートツール**「極 医療文書」**です。AIが紹介状のドラフトを迅速に作成し、先生の確認・修正時間を大幅に短縮することを目指しています。電子カルテ連携も不要で、手軽に導入できる点も特徴です。もし、文書作成業務の効率化にご興味があれば、ぜひ一度チェックしてみてください。
それでは、他の医療文書の保存に関するトピックも見ていきましょう。
電子カルテでの保存:注意すべき3つの原則
電子カルテ等で医療文書を電子的に保存することは、厚生労働省のガイドラインの下で認められています。スペースの節約や検索性の向上などメリットも大きいですが、以下の3つの原則を満たす必要があります。
- 真正性(Authenticity): データが改ざんされていないこと、作成の責任が明確であること。
- 見読性(Readability): 必要時にすぐ画面表示や印刷ができること。
- 保存性(Preservation): 法定期間中、データが消えたり壊れたりせず、復元可能な状態で安全に保管されていること(バックアップ含む)。
これらの原則を守るためには、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠したシステムの利用と運用体制(アクセス管理、セキュリティ対策、バックアップ等)が求められます。導入・運用にはコストや手間もかかりますが、適切に行えば非常に有効な手段です。
法定期間を超えて保存した方が良い?「20年」が一つの目安
法定期間(カルテ5年、その他3年)はあくまで「最低限」の義務です。実務上は、より長期間の保存が推奨されています。
- 理由1:民法改正による消滅時効: 医療過誤などに関する損害賠償請求権の時効は、「損害および加害者を知った時から5年」または「不法行為の時から20年」と定められました。法定の5年保存では、この20年に対応できないリスクがあります。
- 理由2:日本医師会の指針: 日本医師会は、電子化の流れも踏まえ、診療録等の永久保存を推奨しています。
- 理由3:臨床上の有用性: 長期的な患者管理や将来の研究に役立つ可能性があります。
特に電子カルテであれば、20年以上の長期保存も現実的です。
保存義務違反のリスク:罰金よりも怖いこと
もし医療文書の保存義務に違反した場合、医師法違反による罰金(50万円以下)が科される可能性があります。しかし、保険診療を行うクリニックにとって、より深刻なリスクは保険医療機関指定の取消です。
療養担当規則の違反(記録不備を含む)が、個別指導や監査で指摘され、悪質と判断された場合、保険診療を行えなくなる可能性があります。これはクリニック経営にとって致命的な打撃となりかねません。適切な文書保存は、クリニックを守るための重要な砦なのです。
まとめ:実践的なチェックポイント
- 基本ルール: カルテは完結の日から5年、その他保険関連記録は3年。
- 「完結の日」を意識: 診療継続中は保存期間のカウントが始まらない。
- 電子保存: 3原則(真正性・見読性・保存性)とガイドラインを遵守。
- 長期保存の推奨: リスク管理のため「20年」が一つの目安。電子カルテなら実現しやすい。
- 紹介状: 3年を目安にカルテと共に保管。
- 最大のリスク: 保険医療機関指定の取消。
医療文書の管理は煩雑ですが、ルールを正しく理解し、院内の体制を整えることが重要です。
文書作成の効率化で、管理体制を見直す時間を
ここまで医療文書の「保存」について解説してきましたが、やはり日々の診療の中で文書業務に多くの時間を割かれている先生方も多いと思います。適切な「保存」体制を維持するためにも、日々の「作成」業務の効率化は重要です。
AIが紹介状作成をサポートする**「極 医療文書」**は、まさにその「作成」にかかる時間を大幅に削減し、先生方の負担を軽減することを目指したツールです。紹介状作成が楽になれば、今回お話ししたような文書の適切な「保存」管理について考えたり、他の重要な業務に集中したりする時間を生み出すことができます。
電子カルテ連携不要で簡単に始められますので、ご興味があればぜひ一度、詳細をご覧ください。
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な対応については、必ず弁護士や専門家にご相談ください。