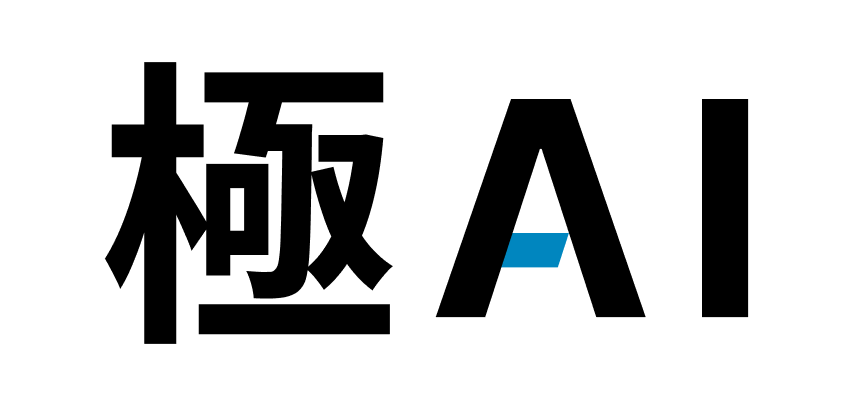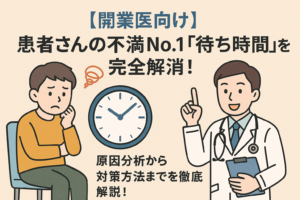【2025年度版】診療情報提供料(II)の算定、もう迷わない! (I)との違い・算定要件を完全ガイド
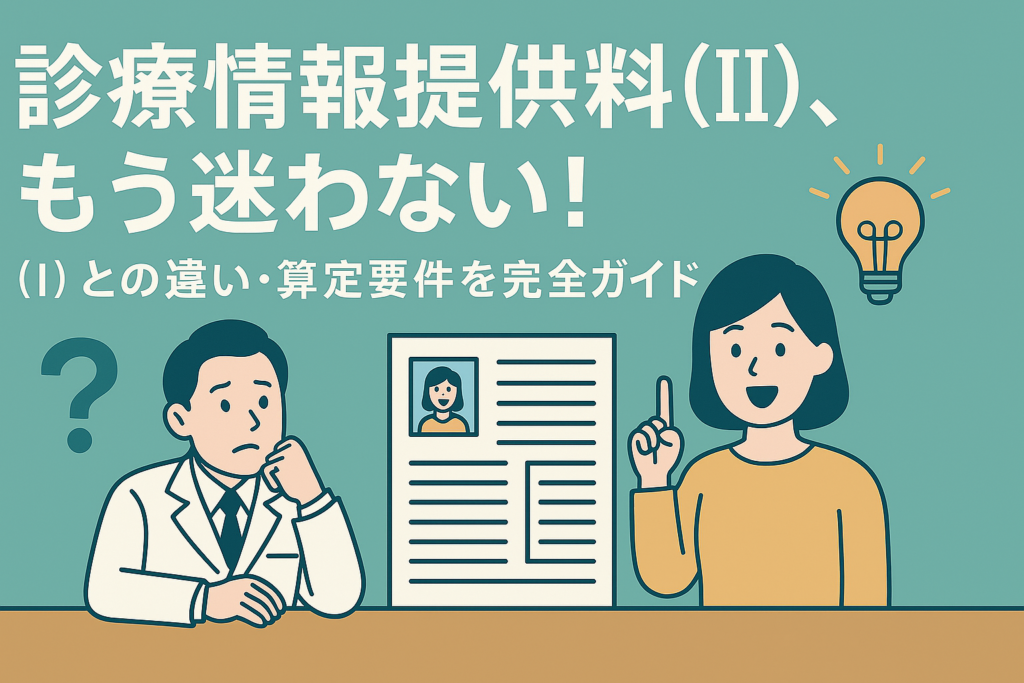
「患者さんからセカンドオピニオンのために資料が欲しいと言われたけど、どの診療情報提供料を算定すればいいんだろう?」 「診療情報提供料(I)と(II)の違いがいまいち分からない…」
日々多くの患者さんと向き合う開業医の先生方の中には、このように感じたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に「診療情報提供料(II)」は、患者さんのセカンドオピニオンを支援する際に算定するものですが、「診療情報提供料(I)」との違いが分かりにくく、算定に迷うケースもあるかもしれません。
この記事では、そんな先生方のために、「診療情報提供料(II)(B010)」について、その基本から具体的な算定要件、混同しやすい「診療情報提供料(I)(B009)」との違い、そして実践的な算定の流れまで、分かりやすく解説します。 適切な算定は、先生方の正当な評価につながるだけでなく、患者さんが納得して治療を選択するための大切なサポートにもなります。ぜひ、日々の診療にお役立てください。
1. 診療情報提供料(II)とは? ~患者さんの「知りたい」に応える評価~
診療情報提供料(II)(B010) は、一言でいうと、「患者さんやご家族が、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞きたいと希望した際に、そのために必要な診療情報を提供した場合に算定できる点数」 です。
ポイントは、あくまで 「患者さん側の希望」 が起点となっている点です。先生が治療継続や専門的検査のために他の医療機関へ紹介する「診療情報提供料(I)」とは、その目的が根本的に異なります。診療情報提供料(II)は、患者さんが主体的に治療方針の選択に関わることをサポートする先生の労務を評価するものなのです。
【知っておきたい注意点】
- 算定するのは「情報を提供する側」の先生です。 セカンドオピニオンを行う側の医師が算定するものではありません。
- セカンドオピニオン外来は通常「自費診療」です。 相談が主体で治療を行わないため、保険適用外となることが一般的です。情報提供の際に、この点も患者さんに伝えておくと親切でしょう。
2.【重要】これを満たせばOK!診療情報提供料(II)の算定要件
では、具体的にどのような場合に診療情報提供料(II)(500点)を算定できるのでしょうか?以下の要件をしっかり確認しましょう。
- 患者さん・ご家族からの明確な「希望」があること
- これが絶対条件です。「他の先生の意見も聞いてみたいのですが、資料をいただけますか?」といった、患者さん本人またはご家族からの セカンドオピニオンを目的とした情報提供の申し出 が必要です。
- たとえ先生からセカンドオピニオンを提案した場合でも、最終的に患者さん側からの主体的な希望が確認できなければ算定できません。
- 必要な情報を「患者さん・ご家族」に直接交付すること
- 作成した診療情報提供書や検査データなどの資料は、セカンドオピニオン先の医療機関に直接送るのではなく、患者さん本人またはそのご家族に手渡す 必要があります。患者さんがその資料を持参して、自分で選んだ医療機関を受診する流れになります。
- 診療録(カルテ)に「希望があった旨」を記載すること
- 「〇月〇日、患者(または家族)よりセカンドオピニオン希望のため、診療情報提供の依頼あり」 といった記録が 必須 です。これが算定の根拠となります。記録がない場合、審査で認められない可能性があるので注意が必要です。
- セカンドオピニオンに必要な情報を提供すること
- 単に紹介状を書くだけでなく、セカンドオピニオンを担当する医師が適切な助言をするために 必要かつ十分な情報 を提供する必要があります。具体的には以下のものが挙げられます。
- 診療情報提供書
- 治療計画
- 検査結果(血液検査、病理検査報告書など)
- 画像情報(レントゲン、CT、MRIなどのフィルムやデータ)
- その他、診断名、症状経過、現在の治療内容など
- 単に紹介状を書くだけでなく、セカンドオピニオンを担当する医師が適切な助言をするために 必要かつ十分な情報 を提供する必要があります。具体的には以下のものが挙げられます。
- その他のポイント
- 入院中の患者さんでも、外来患者さんと同様に算定可能です。
- 情報を提供する医療機関側に、特別な施設基準の届け出は必要ありません。
- 交付した診療情報提供書や添付資料の 写しは、診療録に添付 しておきましょう。(記録管理として重要です)
3. 算定点数と算定回数
- 算定点数: 500点
- 算定頻度: 患者さん1人につき、月に1回まで
- これは暦月(1日~末日)での制限です。
- 例えば、患者さんが提供された情報をもとに、同月内に複数の医療機関でセカンドオピニオンを受けたとしても、情報を提供した元の医療機関(先生のクリニック)が診療情報提供料(II)を算定できるのは、その月で1回のみです。
4. もう迷わない!「診療情報提供料(I)」と「(II)」の違い
ここで、混同しやすい「診療情報提供料(I)(B009)」との違いを整理しておきましょう。これが分かれば、算定で迷うことが格段に減るはずです。
| 項目 | 診療情報提供料(I) (B009) | 診療情報提供料(II) (B010) |
|---|---|---|
| 目的 | 医師の判断に基づく紹介・連携 | 患者・家族の希望に基づくセカンドオピニオン支援 |
| きっかけ | 主に医師の判断(患者同意は必要) | 患者・家族の希望 |
| 基本点数 | 250点 | 500点 |
| 加算 | 多数あり(紹介先、情報内容による) | なし |
| カルテ記載の重要点 | 紹介の必要性、提供情報 | 患者・家族からの希望があった旨、提供情報 |
| 主な場面 | 転院、専門医へのコンサルト、検査依頼、福祉連携 | 患者が治療方針等で他の医師の意見を求める場合 |
【ポイント】
- 誰の意思が起点か? → (I)は医師、(II)は患者・家族
- カルテに何を書くか? → (I)は紹介理由、(II)は「患者希望あり」
【こんなケースは?】 患者さんがセカンドオピニオンを希望し、先生が情報提供して診療情報提供料(II)を算定。その後、セカンドオピニオンの結果を受けて患者さんが転院を希望し、先生が改めて転院のための紹介状(診療情報提供書)を作成・提供した場合。この転院のための紹介状に対しては、診療情報提供料(I) が算定可能です。目的が異なるため、それぞれ算定できる場合があります。
5.【実践編】明日から使える!算定手続きとカルテ記載のポイント
最後に、診療情報提供料(II)を算定する際の具体的な流れと、診療情報提供書の書き方のポイントを見ていきましょう。
《算定までの5ステップ》
- 【確認】 患者さん・ご家族から「セカンドオピニオンのため」の情報提供希望があることを確認します。
- 【準備】 診療情報提供書と、必要な添付資料(検査結果、画像データ等)を用意します。
- 【記録】 診療録に**「患者(家族)よりセカンドオピニオン希望あり、〇〇(資料名)を提供」**のように、希望があった旨と提供した資料の内容を 必ず記載 します。
- 【交付】 書類一式を患者さんまたはご家族に手渡します。
- 【請求】 レセプトで、医学管理料の区分に「B010 診療情報提供料(II) 500点」を算定日とともに記載して請求します。
《診療情報提供書の書き方(B010用)》
セカンドオピニオン用の診療情報提供書に 決まった様式はありません が、助言を行う医師が的確な判断を下せるよう、以下の項目を網羅することが望ましいです。
- 基本情報: 患者氏名、生年月日、連絡先、提供元医療機関名・連絡先、担当医氏名
- 宛名: 患者さんに直接渡すため、「患者様交付用」としたり、特定の宛名なしでも構いません。
- 【重要】目的: 「患者様(またはご家族)のご希望により、セカンドオピニオンを目的として診療情報を提供いたします」 といった趣旨を 明確に記載 しましょう。これが(II)算定の根拠を補強します。
- 診療情報:
- 診断名
- 主訴、現病歴、症状経過
- 既往歴、家族歴
- 主要な検査所見(血液、病理など)
- 画像所見(レントゲン、CT、MRIなど。所見概要を記載し、データは別途添付)
- 現在の治療内容(処方薬、処置など)
- 提供元医師(先生)による評価と治療方針案
- 添付資料: 添付した資料の一覧(例:画像データCD-ROM 1枚、病理標本プレパラート〇枚、検査結果コピー〇枚)
- その他: 作成年月日、医師署名・捺印
既存の紹介状様式を参考にしつつ、「目的」欄をしっかり記載することがポイントです。
▼ 医療文書作成の時間を、もっと短縮したい先生へ ▼
とはいえ、セカンドオピニオン用だけでなく、日々の診療で発生する様々な紹介状や情報提供書。診断名、経過、検査結果、治療方針などを毎回正確に、かつ分かりやすく記載するのは、忙しい診療の合間ではなかなかの負担ですよね。診療情報提供料(I)と(II)の使い分けは理解できても、その都度書類を作成する 時間そのものを短縮したい 、と感じている先生も多いのではないでしょうか。
もし、こうした 医療文書作成にかかる時間を大幅に削減し、もっと患者さんに向き合う時間やご自身の時間を確保したい とお考えなら、AIを活用した紹介状作成支援サービスを検討してみるのも一つの方法です。
例えば、**AI紹介状作成システム『極 医療文書』**は、「使えば分かる」をコンセプトに、先生が入力した簡単な情報をもとに、AIが自然で質の高い紹介状や診療情報提供書を自動生成します。 独自開発の高性能AI を搭載し、電子カルテとの連携も不要 なので、導入の手間なくすぐに使い始められるのが特徴です。先生の意図を汲み取り、適切な文書作成をサポートすることで、 日々の紹介状作成に要する時間を大幅に削減 し、先生方の業務負担を劇的に軽減することを目指しています。
ご興味があれば、ぜひ一度『極 医療文書』がどのように先生の時間を生み出すのか、詳細をご覧になってみてください。
6. まとめ:適切な算定で、患者さんの納得のいく医療選択をサポート
診療情報提供料(II)は、患者さんの「知る権利」「自己決定権」を尊重し、納得のいく治療選択をサポートするための重要な評価制度です。
今回解説したポイント、特に、
- 算定の起点は「患者さん・ご家族の希望」であること
- 情報は「患者さん・ご家族へ」交付すること
- カルテへの「希望があった旨」の記載が必須であること
これらをしっかり押さえ、診療情報提供料(I)との違いを理解することで、自信を持って適切に算定できるようになるはずです。
日々の診療でセカンドオピニオンに関する相談を受けた際には、ぜひこの記事を参考に、適切な情報提供と算定を心がけていただければ幸いです。そして、もし書類作成業務の効率化にご関心があれば、極 医療文書のようなAIツールの活用も検討してみてはいかがでしょうか。